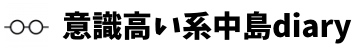高校2年の秋、僕はオタクになった。
毎日毎日、ご飯を食べるときもスマホでアニメを観て、学校でも休み時間にひとりイヤホンを付けひたすら見まくっていた。
こんなはずじゃなかった。何を隠そう中学生までの自分はオタクに人権はないと思っていた。
実在しない二次元のキャラに萌えるなんて意味不明だし、何より中学校にいたオタクはみな根暗でハキハキしてないし、何より俺はお前らとは違う感を漂わせていた。オタクのくせに。
暴力が支配する僕の中学校でオタクに市民権はなかった。不良がラノベを取り上げ「お前こんなの読んでんのかよ!きしょ!」とからかい、オタクが恨めしそうな目でそいつを見ていた。
そんな光景を見ながら僕はまったくオタクに同情しなかった。ほんとにキショい。そんなふうにしか思えなかった。
あれから数年経ち、どういうわけか僕はオタクになった。これは完全に環境のせいだ。僕の高校は男子校で、変なやつしかいなかった。そしてオタクがめちゃめちゃ多かった。中学のときはクラスに2人しか居なかったオタクが高校ではクラスの半分くらいいた。校内放送ではアニソンやボカロが流れ、休み時間にオタ芸を練習してるやつらもいた。
僕ははじめは抵抗した。市民権を得たとしてもオタクはオタクだ。高校生にもなって2次元に恋するなんて頭沸いてる。
だが長くは持たなかった。僕は男子校の呪いにかかってしまった。
現実の女の子に希望を持てなくなったある日、友達が僕に
「やっぱ3次元の女の子は夢ないわ~2次元に限るよ!」
と言ってきた。何言ってんだコイツと思ったが言われるがままにそいつが勧めてきたアニメを観た。タイトルは「中二病でも恋がしたい」
高校2年、秋のことだった。
それを境に僕はオタクになった。
「闇の炎に抱かれて消えろ!!」といいながら六花たんかわゆす~なんて感じで画面にかじりついた。
「ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛心がぴょんぴょんするんじゃあ~↑↑↑」とごちうさを観てリゼちゃん推しになり、月刊少女野崎くんで爆笑し、アイマスを片っ端から観て天海春香推しになった。のんのんびよりを観ては田舎暮らしに憧れ、初音ミクの造形に美の真髄を見出し、部屋に彼女のポスターを貼り付け、秋葉原のUFOキャッチャーでフィギュアをGETするために一人出かけた。iPodのJ-POPは記憶の彼方に忘れ去られ、アニソンとボカロが容量を圧迫した。
えらい変わりようである。周りのまだZ軸をその身に宿している友人にはキモがられた。一方オタクの友人は僕を歓迎してくれた。オタクになったとはいえ僕はそこまでガチではない。毎日アニメを観て毎月秋葉原にグッズを買いに出かける程度で、にわかと言われれば確かにそうだ。
それでも彼らは僕を優しく迎え入れてくれた。僕の世界がまたひとつ増えた。
特に僕が好きだったのがラブライブだった。推しは西木野真姫一択。

毎週の放送を楽しみにし、推しの登場を心待ちにしていた。カラオケでは声が枯れるまでμ'sの曲を歌った。聖地巡礼もし、神田明神にも行った。
ラブライバーの一端だったわけだ。
今まで嫌っていた世界にどっぷり浸り、僕は新しい世界を心ゆくまで楽しんでいた。
しかし物事には必ず終わりが来る。人はいつか死ぬし、この宇宙もやがて滅びる。それと同様に、僕のオタク人生も終わりを迎えた。
高三の秋、好きな子が出来た。
他校の女子高の子で、文化祭で知り合った子だった。みなさんの期待を裏切るようだが、僕は男子校にいたけど常に仲のいい女の子はいた。特に文化祭は出会いの場で、気になる子がいれば声をかけ、逆に向こうから声をかけてくれることもあった。
ただどの子とも長続きしなかった。文化祭の一瞬で知り合っただけで互いのことをよく知らず、遊んでも会話が合わなかったりして向こうの期待を裏切ったり、自分もなんか違うなと思うことが多かった。
そんな感じでどうしてもこうも現実の女の子は難しいのかと悩んでいたこともあり、僕はオタクになってしまったのもある。
しかし高三の秋、好きな子ができた。
文化祭で連絡先を交換し、一緒に映画に行ったりした。
高校生らしいことをし、高校生らしい会話を楽しんだ。
幸いなことにとても気が合い、会話も弾んだ。
ちなみに僕は大学受験真っ只中だったがそんなの御構い無しに遊んだ。
相手の子は一つ下の高二だった。
そして僕らは付き合った。
その過程はわざわざ語る必要はないだろう。
しかし付き合いだして2ヶ月ほどたったある日、いつものように彼女の家近くのファミレスでご飯を食べていた時にこんなことを言われた。
「正直オタクって知った時もう関わらないようにしようかと思った笑」
びっくりした。さらに彼女はこう続けた。
「私は二次元に憧れる気持ちは一ミリもわからないし気持ち悪いとしか思えない。」
でも個人の自由だから仕方ないけど。と彼女は続けた。物事をはっきりいう性格だった。ただ彼女の言葉はナイフのように僕の心を突き刺した。
当時の僕はぱっと見だとゴリゴリのスポーツマンで、とてもオタクとは思えない見た目だった。逆にそのギャップが良いと思っていたし、にわかファッションオタクの皮を被っていたとも言える。でもただ純粋にアニメが好きで、そのキャラクターが好きだった。
ただこの世界を知らない人からしたら僕らは気持ち悪い存在でしかない。
確かに二次元に憧れるのは意味がわからないだろう。
どっかの政治家もそのうち『オタクは生産性がない』と言い出すかもしれない。確かに二次元を愛でてもそこから何か生まれるわけではない。はたから見たら。
ただ当のオタクは違う。当時の僕にとってアニメに夢中になることは心の好きだった。辛い部活や受験勉強の合間に観るアニメに心を救われていたし、月に一度秋葉原に出かけることが楽しみで仕方なかったし、好きなコミックの販売日を待つことが生きる理由だった。推しの躍動する姿が僕に勇気をくれた。たとえ彼女たちが次元を超えられなくとも、しっかりとそのエネルギーは僕の胸に届いていた。
アイドルという単語は「偶像」「崇拝の対象」「憧れのまと」という意味を持つ。僕にとって推したちはアイドルだった。そして現実には存在しない、現実を超越した僕らの理想が具現化したものだったんだ。
オタクはその熱狂的な偏愛ゆえにキモがられるが、僕はその気持ちがわかる。何かを心の拠り所にすれば人は強く生きられる。その拠り所が人によっては家族だったり、彼女だったり、友達だったり、仕事だったり、音楽だったりするわけで、それがたまたま二次元だったのがオタクなんだ。
彼ら、そして当時の僕はオタクとしてアニメを愛で、憧れの気持ちを抱き、救われてきた。その本質は他のオタクでない人たちとなんら変わりはない。
だけど。だけどだ。やはり分からない人からしたらオタクはキモい。キモいんだ。
人は分かり合えないものには嫌悪感を抱く。当時の僕が三次元を愛でるドルオタを白い目で見ていたのと同様、陽キャは陰キャを蔑み、陰キャは陽キャを恨む。
僕のようにアニメに熱中したことがない人はオタクの気持ちは理解できない。彼女からすれば自分と付き合っているのに決して画面から出てくることのない存在しない女の子に憧れを抱くとは何事かという気持ちだったろう。
そして僕は二次元を捨て三次元をとった。僕がオタクをやめた日だった。
彼女の言葉を聞いてから、徐々にアニメへの熱が失われていった。
元はと言えば三次元の女の子に失望して見始めたアニメだった。
理想的な女の子と出会えた今、もはやアニメを観る必要はない。
毎日見ていたアニメは週に一度の頻度になり、やがてつまらなく感じて来た。
年が明けてからは受験に追われ、もうアニメのことなどすっかり忘れていた。
本棚に積んだコミックの山は埃をかぶり、飾ってあったフィギュアはクローゼットの中に押し込まれた。
結局受験には失敗し、浪人をした。その一年、一度もアニメを見なかった。目の前の勉強で頭がいっぱいだった。
高校生の頃は大学に行ったらその有り余る時間を使ってアニメを見まくり、バイト代でイベントに参加しまくると心を決めていたのに、入学後アニメに熱中することはなかった。
結局その彼女との関係は終わりを迎えたが、再び僕がオタクに戻ることはなかった。
そして今年の夏も、コミケに参加することなく涼しい部屋でこの記事を書いている。
ここまで書いてなんだか懐かしい気持ちになり、クローゼットの中からかつて集めていたアイマスのファイルを引っ張り出した。

確か当時、コンビニで対象の商品を買えばこのファイルが貰えたんだっけ。
どこに行っても売り切れで、Twitterで情報を集め自転車で何キロも漕いで隣町のコンビニまで行きやっと手に入れたことを覚えている。
何が僕をそこまでさせたのだろう。
僕には何が見えていたんだろう。
僕は何がしたかったんだろう。
あの頃の気持ちを取り戻すことはできない。オタクを否定されたあの日から僕は変わった。変わると同時に一つの居場所を失った。もう二度とあの世界に浸ることはないだろう。
クローゼットから出てくる埃まみれのファイルやフィギュアを手に取りながら、そんなことを思った。
コミケ最終日で賑わうタイムラインを眺めながら、あの頃を思い出した。始発電車からオタク走りで改札を駆け抜ける彼らは滑稽に見えるかもしれないが、これから彼らが向かう先には夢の世界が広がっているんだ。
<参考記事>