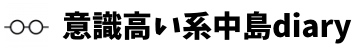藤原由佳はどこにでもいる平凡な女子中学生だった。
文芸部に所属し、毎日授業後に部室に行っては好きな小説を読む。嫌いな科目は数学と体育。得意な科目は国語と美術。どこまでも平凡な、石を投げれば当たりそうな、あたりさわりのない中学生だった。
野口真波は日によく焼けた色黒で活発な生徒だった。
野球好きな両親の影響で小学3年生から地元の少年野球チームに所属し、中学では迷わずソフトボール部に入った。よく笑う、歯の白い、愛想のいい誰からも好かれる女子中学生であった。
原田咲は絵に描いたような優等生だった。
小学校の頃から学級委員をつとめ、成績は常にトップ。母親の勧めで中学受験をする予定だったが、居心地のいい地元の公立中学校への進学を決め、今はバレー部に所属している。密かに彼女に恋心を抱く男子が多いことを、原田咲は少なからず自覚していた。
平沢香澄は部活には所属せず、放課後はすぐに家に帰り、身支度を整え、都心にある音楽教室に通う生活をしていた。
両親は音楽家。物心つく前からピアノを弾いていた彼女は、そのまま有名なピアノ奏者の教室に小学校1年生のときから通い、数々のコンクールで優勝していた。この前は関東のピアノコンクールで優勝し、地元の新聞の一面を飾った。
一見全く違う生活を送っていた彼女たちは、公立中学校の無作為にクラスを振り分ける仕組みで、中学二年生のとき、たまたま同じクラスになった。名前の順で座席が振り分けられ、彼女たちは縦に4人続きの席になった。
部活も習い事も、生まれ育った環境も違う彼女たちがどういう経緯で仲良くなったのかは分からない。席が近いからと言う理由で、何がきっかけという訳でもなく、自然と話すようになったのであろう。
そして彼女たちは自分たちの生活にそれなりに満足していた。
藤原由佳にとってはサリンジャーを読んでいるときが幸福な時間であり、野口真波にとっては試合で相手ピッチャーの放る球をまっすぐセンターに弾き返す瞬間が何よりも楽しく、原田咲にとっては自分の一挙一動に見惚れている男子の視線を感じるだけで自尊心が満たされ、平沢香澄は数百人の前でピアノを演奏し最後の栄冠に輝き金色のトロフィーを受け取り瞬間、何にも変えがたい満足感に浸ることができ、それこそが彼女の生きる理由だと心の底から感じていた。
何が彼女たちにある衝動を与えたのか、今となっては誰も知る由がない。
藤原由佳がどこから金魚を持ってきたのか、野口真波が何で有刺鉄線を切断したのか、原田咲がどうやって厳格な両親の目を盗んで夜中に家を抜け出したのか、あまり運動が得意でない平沢香澄がなぜプールに飛び込むなど大胆なことができたのか、今となっては誰も分からない。
ただ確実なことは、暑かったあの年の夏、誰もいない学校のプールに夜中、女子中学生四人組が現れ、五百匹もの金魚をそこに解き放ち、彼女たちもプールに飛び込んだという事実だけだ。
藤原由佳はその日、自室のベットに横になりながら、ヘルマンヘッセの車輪の下を読んでいた。彼女にとってハンスの堕落していく様は、まるで自分の行く末を暗示されているかのようで居心地の悪さを覚えたのと同時に、いっそのこと彼のように悩みに身を任せいくところまでいってしまえたらどんなに楽なのだろうかと、自暴自棄かつ自由な妄想に耽っていた。
野口真波は自宅の玄関で入念にグローブを磨いていた。翌日朝9時に隣町の中学校に行き、秋の新人戦に向けた大切な練習試合に臨む予定だった。先月6月の大会で3年生は引退し、部活は野口真波たちの代になった。副部長になった彼女にはそれほど大きな責任はなかったものの、試合では誰よりも結果を出さなくてはならないという信念を持っていた。サードを守る自分に飛んできた打球は全て止めてやろうと、丹念にグローブに油を染み込ませていた。
原田咲は母親と9歳の弟と晩御飯を食べていた。その日のメニューは弟の大好きなカレーだった。仕事で帰りが遅い父の分を鍋に残し、母親と弟と咲の三人はいつものようにテーブルを囲み、ニュース番組を見るでもなく聴くでもなくただ流しながら、無愛想に首を振る扇風機に当たっていた。
平沢香澄は電車に乗っていた。二週間後に京都で大きなコンクールを控えていた彼女は最後の追い込みのためより厳しいレッスンを受けていた。連日大量の宿題を課され、夜中の2時まで眠れない毎日。今日は明け方4時まで楽譜とにらみ合い、朝10時からのレッスンにわずかな睡眠時間で向かった。唯一の助けは一昨日から夏休みが始まったということだった。どうにか座席に座れた平沢香澄はすぐさま眠りに落ちた。
そんな彼女たちの携帯に藤原由佳から一通のメッセージが来たのは、野口真波がグローブ磨きを終え素振りを始めてしばらくたち、原田咲が晩御飯を済ませシャワーを浴びるため部屋に着替えを取りに行き、平沢香澄が眠りから覚め、最寄駅の一つ前の駅に到着した瞬間だった。
「金魚をプールに入れて一緒に泳いでみない?きっと綺麗だと思うの。」
いつも休み時間、自分の席で聞いたこともない作家の小説を読み入っていた藤原由佳。行動的とは言えない彼女が、どんな経緯でそんな突拍子もない考えに至ったのか検討もつかなかったが、野口真波、原田咲、平沢香澄の三人は何を感じてか、すぐにプールに向かった。
野口真波、原田咲は自宅から自転車で。平沢香澄は最寄駅から徒歩で。藤原由佳はどこから来たのかは分からない。待ち合わせの時間を決めるのでもなく、21時過ぎ頃、四人は校門を乗り越え、南京錠で施錠されたプールの有刺鉄線の扉の前に集まった。
月が高く、明るい夜だった。
プールの水面には月の明かりが反射し、そこだけ切り取ったら太平洋の真ん中と言っても信じてもらえるような、きらめきをしていた。その光はとても優しく、誰かに「月が光っているのはね、太陽の光を反射しているからなんだよ」と言われても信じられないくらい優しいものだった。
「これを持ってきたの」
藤原由佳の両手には、大きな大きなバケツが吊り下げられており、そのバケツいっぱいに大小様々な色をした金魚が入っていた。
「これをプールに入れて一緒に泳いでみたら、とても綺麗だと思うの。」
「そうね。」
「きっと綺麗でしょうね。」
「今日はこんなに素敵な夜だし。」
4人の目はどれも金魚を見てはいなかった。妖艶にきらめくプールの水面も、穏やかに輝く月も、どれも彼女たちの視線は捉えていなかった。
気がつくと4人はプールサイドにいた。後ろには切断された有刺鉄線の扉が申し訳なさそうに半分開いており、初夏の涼しい風に吹かれて揺れていた。
「さあ、いってらっしゃい。」
藤原由佳が右のバケツを持ち上げ、プールに中身を注ごうとした。その腕を野口真波と、原田咲と、平沢香澄が支えた。傾いたバケツから水が流れ落ち、少し後から、金魚が、為す術もなくプールへと飛び込んでいった。
続いて藤原由佳の細い左腕がもう片方のバケツを持ち上げた。再び残りの三人が彼女の腕を各々支え、バケツが傾くや否や、水とともに金魚がプールへと落ちていった。
誰もいない25mプールは、彼女たちの想像よりもはるかに大きかった。
金魚はいつの間にかプールの闇へと消え、水面にはごくわずかしか見えなかった。
「あら、こんなものなのね。」
藤原由佳はそう言って少し肩をすくめると、なんのためらいもなく着ていたシャツを脱ぎ、下着も取り、そのまま両足で踏ん張って跳ね上がり、プールの中に足から飛び込んだ。
「ザッバーン」
それにつられて野口真波、原田咲、平沢香澄の3人も無言で上半身裸になり、藤原由佳の後に続いて、プールに飛び込んだ。
普段からプールが好きな野口真波は、水に飛び込むなりいきなり目を開けた。水泡の間に、赤、黒、白に輝く金魚がところどころに見えた。その瞬間、野口真波は明日の試合のことを思い出した。しかしすぐに消えた。自分にとって、今この瞬間はこの先何十年生きても体験できないものなのだと、目の前を漂う無数の金魚を見て、彼女は悟った。野口真波は瞬きすら忘れ、金魚を1匹1匹目で追っては、その姿を目に焼き付けた。
原田咲は、水に入った瞬間、笑いが込み上げてきた。自分は今、夜中の学校に忍び込んでプールに入り、金魚と一緒に泳いでいる。普段、先生の言うことを素直に聞き、成績も首位だった絵に描いたような優等生の彼女からしたら、ありえないことだった。
「ねえ。私、こんなにいけないことしてるのよ。」
目の前を漂っていた白い金魚に彼女はそう語りかけた。いつもなら容姿端麗な彼女の言葉に、クラスの男子誰もが耳を傾けたが、彼女が水中で放った言葉は誰にも届かず、泡になって水面へ消えていった。白い金魚も、何事もなかったかのように目の前を通り過ぎていった。
原田咲はそのとき、生まれて初めて自分の意思で、人の目を気にせず、自分の人生を楽しむことができていると感じた。
平沢香澄の脳内には、地面を蹴って飛び上がった瞬間から、バッハのゴルトベルク変奏曲アリアが流れていた。それは彼女が小学校4年生のときに、初めてコンクールで優勝したときに弾いた曲だった。なぜアリアが今、頭の中で急に再生されたかは分からない。
運動の苦手な彼女は気がつくと水の中におり、目を開けると周りに無数の金魚が漂っていた。自分はこの先ずっと、アリアを聞くたびに、そしてプールや金魚を見たり、そういった単語を聞くたびにこの光景を思い出すのだろうと、14歳ながらに感じ取った。
一番最初に飛び込んだ藤原由佳は、入水した瞬間、自分はここで死ぬのだと思った。
7月下旬、昼間は溶けるように暑かったが、夜となるとまだ涼しい。連日の雨でプールの水は思ったよりも冷たく、飛び込んだ瞬間、息が止まり体が硬直した。
5秒だったのか30秒だったのか、1分だったのか分からないが、ようやく目を開けたとき、目の前に1匹の金魚が浮かんでいた。
真っ赤な金魚が、藤原由佳の目の前に浮かんでいた。
金魚の真っ黒な目は、彼女の目を見るのでもなく、その焦点の合わない目を小刻みに動かしていた。この金魚はこの後どうなるのだろうか。酸欠で死ぬのだろうか、それとも排水溝に吸い込まれてどこかの川に流れ着くのだろうか、それとも誰かに拾われ、小さなガラスの水槽の中で短い一生を終えるのだろうか。
藤原由佳の頭に思い浮かんだのは、他でもない数十分前まで自宅で読んでいたヘッセの車輪の下の主人公ハンスだった。彼女はついさっきそれを読み終えたばかりだった。
「私もハンスのように、このまま溺れるのかもしれない。」
動かそうと思えば、藤原由佳はいつでも手足を自由に動かせた。7月下旬のプールの寒さは、彼女の四肢を硬直させるには十分な冷たさではない。しかし彼女はあえて沈むがままに身を任せた。
このまま沈みきってしまおうなどと考えてはいなかったが、この続きに何があるのか、見てみたかった。
いつの間にか仰向けになった藤原由佳は、月に照らされた水面を見上げながら、ゆっくりとプールの底に沈んでいった。
そのとき、藤原由佳は、想像を超える膨大な数の金魚が水面に漂っていることを悟った。いつの間にか目の前にいた真っ赤な金魚は見えなくなっていた。
こうして底の方から見上げると、バケツに入れて運んできた500匹もの金魚が、ゆらゆらと水面を漂っているのが見えた。
赤、白、黒、金。
月の光に照らされ、そのどれもが星のようにきらめいていた。
「なんて綺麗なんだろう。」
ぼんやりとした意識の中、藤原由佳は一人その光景に陶酔していた。
「金魚の星空だ。」
小説を読んでも決して味わうことのできない、非現実的ながらも絶対的に現実の光景に、藤原由佳はただただ圧倒され、言葉を失った。
数分後、プールサイドには、野口真波、原田咲、平沢香澄、そして藤原由佳の四人がいた。
泳ぐのが得意な野口真波を筆頭に、原田咲、平沢香澄が手伝い、藤原由佳を引き上げたのだった。
4人は笑っていた。気がつくと、自然と笑顔が溢れていた。誰も何か言葉を発するでもなく、4人の中学校二年生の女子の声が、少し波だった月に照らされた水面に、いつまでもいつまでも、響き渡っていた。
あれから数年が経ち、藤原由佳、野口真波、原田咲、平沢香澄は別々の高校に行き、あるものは大学にいき、あるものは働きだし、それぞれの道を歩んだ。
あの金魚を放った夏のとある日の記憶は、彼女たちから少しずつ消えていき、毎日のように思い出すことはなくなっていった。
それでもふとしたきっかけで、あの日のあのプールの塩素のかすかな匂いと初夏のむっとした蒸し暑い独特な感覚を伴って、彼女たちの記憶は蘇る。
野口真波にとってそのきっかけは、それが一人暮らしを始めた家のすぐ近くの小学校のグラウンドで行われている少年野球で、バットがボールを弾く音であり、
原田咲にとってはそれが同級生からの結婚報告を聞いたときであり、
平沢香澄にとっては、通勤中、いつものようにシャッフル再生し流れてきた曲が、偶然バッハのゴルトベルク変奏曲アリアだったときであった。
そして藤原由佳にとっては、会社からの帰りの電車、最寄駅に到着し、読んでいた小説から目を離し電車から降りて、ふと空を見上げた瞬間であったりする。
あのとき放った金魚がどうなったのか、彼女たちは知らない。
だけど藤原由佳は思うのだ。
あの日、プールの底から見上げた金魚の星空。
今見上げている空の、あの星は、あの日の金魚の生まれ変わりなのかもしれないと。
そんな想像をしながら、藤原由佳は家路を急ぐ。家に帰り、リビングの灯りを付ける。
テーブルの上の鉢には水がなみなみと注がれ、そこには1匹の真っ赤な金魚が泳いでいた。
以上の話は、こちらのニュースを見て、久々にお酒を飲んでいた僕が何を思ったのかいてもたってもいられなくなった結果、夜中2時に急にパソコンを開き、勢いのまま3時間で書き上げたものである。生まれて初めて深夜テンションというものを味わったかもしれない。
また気が向いたらこんなものを書いてみたいな、なんてことを思いながら、今日は昼過ぎまで眠ることにする。
それでは素敵な1日を。

- 作者: ヘルマンヘッセ,Hermann Hesse,高橋健二
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1951/12/04
- メディア: 文庫
- 購入: 9人 クリック: 464回
- この商品を含むブログ (158件) を見る
<オススメの記事はこちらから>