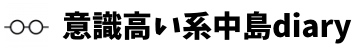御茶ノ水という名前を聞くだけで、僕はあの年の4月の春の陽気を思い出す。
それと同時に、コンクリートから反射する熱でくらくらするほど暑かった夏も、夕日に照らされた落ち葉の上を歩いた秋も、白い息を吐きながら静かに光る月を眺めた冬も、まるで昨日のように思い出すことが出来る。
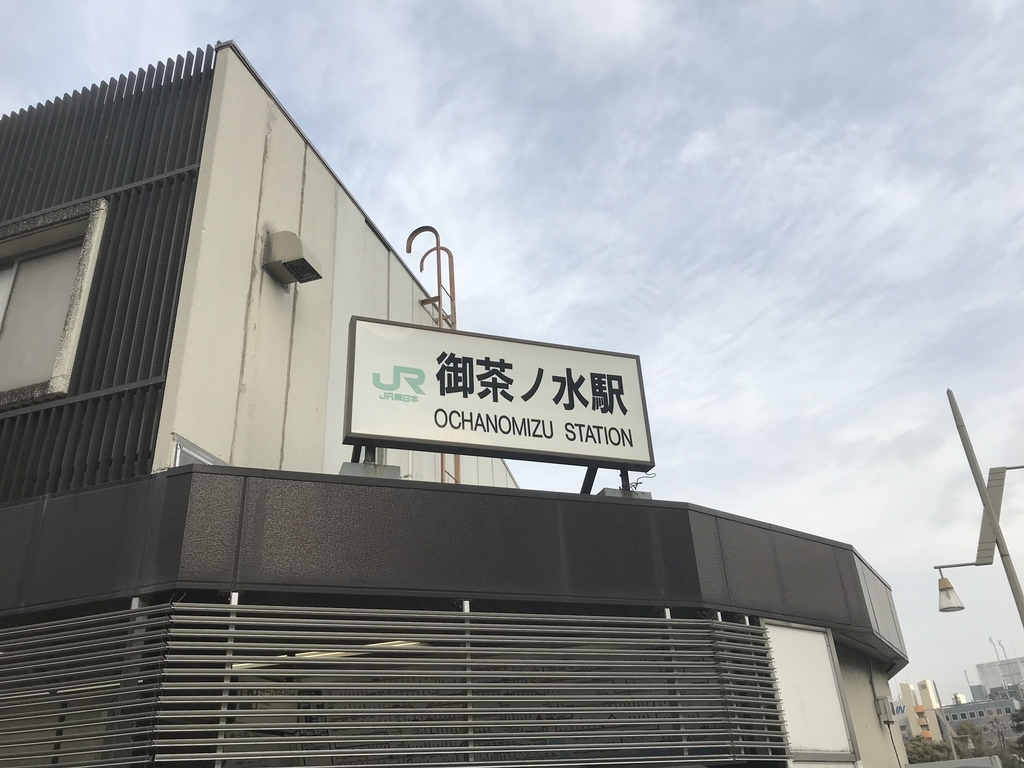
19歳という10代最後の1年をあの場所で過ごしたことは、あれから数年経った今も、鮮明に覚えている。
その多くは楽しい、そして嬉しい思い出ではない。
春。
満開の桜の下、教材をパンパンにつめたリュックを背負い予備校に向かって歩いていた僕の目には涙が浮かんでいた。
夏。
汗だくで歩く僕の右手にはE判定の文字が書かれた模試の結果がぐちゃぐちゃになって握られていた。
秋。
夕日に照らされた落ち葉の上を歩いたあのとき、模試を受ける度に縮まる現役生との差に僕は怯えていた。
冬。
白い息を吐きながら月を眺め駅まで歩いたあの寒い夜、僕は来る本番の試験に、吐きそうなくらい緊張していた。
19歳の1年間ほど辛く孤独な1年はなかった。
現役で大学に受かることを信じて疑わなかった僕にとって、浪人は受け入れ難い事実だった。
自分は浪人した。
そんな現実と向き合いながら机に向かう毎日の繰り返し。
友達は絶対に作らないと決めていた僕は授業が終わるなり誰よりも早く教室をあとにし、地元の図書館に篭もった。
たまの気晴らしに御茶ノ水から少し歩いたところにある三省堂の参考書コーナーに立ち寄ってはパラパラと意味もなく様々な参考書を立ち読みし、それだけで頭が良くなった気になっていた。
御茶ノ水の街は浪人生のためだけの街ではない。
明治大学をはじめ色々な大学のキャンパスが軒を連ねる。
みじめに予備校へ歩く僕の横を、楽しそうに友達や彼氏彼女と歩く大学生を見ては、俺は一体ここで何をしてるんだと、ぐっと涙を堪えた。
街に出てお昼を食べに行けば、そうやって大学生と必ず出くわしてしまう。ガラスのように脆かった僕の精神は、それだけで音を立てて崩れ落ちてしまう危うさを抱えていた。そうはならないよう、いつも母が作ってくれたお弁当を1人、予備校の教室で食べていた。高校生活を終えてなお、息子のためにお弁当を作ってくれ、さらには費用まで出してくれる母そして家族に対し、情けない気持ちと感謝の気持ちで心が溢れてしまいそうだった。
浪人とは不思議なもので、時間の流れが自分の心の状態によって変わる。
気分が乗っている時は、気が付くと3時間があっという間に経っていたなんてこともざらにあった。
一方でどうしてもやる気の出ない日は、10分が1時間にも2時間にも感じられた。
そして受験の日が永遠に訪れないのではないかと急に不安になり、出口の見えない浪人生活に心の底から絶望した。
模試の成績が悪ければ涙を流し、良ければ拳を突き上げて喜ぶ。
感情の振れ幅が大きく、次第にたまっていく疲労。
それを発散する場も時間もない。
もともと1人でいることが好きな僕はあえて1人で勉強することを好んだが、今思い返さば新しい友達の1人や2人、作ってもよかったのかもしれない。
数え切れないくらい模試を受け、数え切れないくらい泣き、早く受験が終わらないかと祈った。1秒でも早くこの監獄から抜け出したい。その思いだけで机に向かっていた。
まだ19年間しか生きていない身ではあったが、あのどうすることも出来ない不安や絶望は、確実に青年の心を蝕んでいった。
しかし10月を過ぎるとその思いは次第に消え、むしろゆっくり時間が過ぎて欲しいとさえ思うようになった。
足りない。
足りない。
足りない。
いくら時間があっても足りなかった。
センター試験に私大対策に二次試験。
やることはいくらでもあった。
ついこの間まで受験の終わりを心待ちにしていた自分はどこかに消え、浪人した目的を果たすため、精一杯やり切ってやろうという気持ちに切り替わったのだ。
ただそのやる気もいつまでも続くものでは無い。
勉強というものに10代最後の貴重な一年を捧げたにも関わらず、解けない問題は必ずある。答えまでの道が全く分からない問題に出くわすたびに、僕はこの一年間何をしていたんだと絶望した。
その度に試験までの残りわずかな時間を数えては時間がないと、後ろから迫り来る現役生、そして同じ浪人生の影に怯え、もしかしたら今年も合格できないかもしれないという恐怖に足がすくんだ。
急に足を早めた時間の流れに戸惑いながら、抑えきれない不安を常に頭に抱えながら、それでも僕は戦うことをやめなかった。
あの1年を通して、僕は人生というものはかくも苦い時間があるのかと身をもって痛感した。
第一志望の合格発表の日、合格者の受験番号が映し出されるページに僕の番号はなかった。
「肩の荷が下りる。」
とはまさにあのことだったのだろう。死ぬほど悔しいはずなのに、すっと一年間僕の上にのしかかっていた重圧から解放された気がした。それは最後の試験を終えたときよりも解放感のあるものだった。
しかし数日後、僕が受けた大学には得点開示という制度があって、自分の点数がいくつだったのか見られるようになっていた。
合格最低点と僕の得点との差は5点だった。
「どうせ全然足りなかったんだろうな。」
本番の手応えが悪かった僕は、かなり低い点で落ちたのだと思っていたのだが、蓋を開けてみるとあと2,3問合っていたら合格していた点数だった。
そのときはじめて悔しいという気持ちが込み上げてきた。
あとちょっとだったのに。
そう思うと、もう涙が止まらなくなった。僕の一年間はなんだったのか。結局第一志望に合格できなかった僕は、ただの負け組じゃないか。何が肩の荷が下りただ。負けてる。負けたんだよお前は。10代最後の貴重な一年を費やしてまでかけた勝負に、お前は負けたんだよ。と。
いくら泣いても、いくら点数を眺めても、その5点が返ってくることはない。
それでも涙はとどまることを知らず、あのとき分からなかった問題はこうして解けばよかったのかもしれないという今更考えても仕方のない後悔が、絶え間なく頭の中を駆け巡った。
あれから数年経った今、改めて御茶ノ水の街を歩くと、あの灰色の毎日が昨日のことのように思い出される。

僕は受験前の最後の授業以来、一度も予備校を訪れていない。
自己採点会や、お疲れ様会のような催しも一切参加しなかった。
僕にとってはあそこはただ大学受験のための勉強をするための箱で、それ以上でもそれ以下でもなかった。
いつも隣に座っていた名前も知らない男子学生とも、クセの強かった講師陣とも、特別もう一度会いたいというような気持ちにはならなかった。
それは彼らにとっても同じだろう。
毎年毎年予備校には新たな浪人生がやってくる。
人には人の、そして自分には自分の地獄がある。
毎日決まって昼に缶コーヒーを飲みながら英単語帳を開いていた隣の席の男子。一度だけ物理のノートを見せてと頼まれたことがあった。神経質そうな色白の青年は僕が見せたノートをゆっくり1文字ずつ理解するように丁寧にルーズリーフに書き写したのち、満足そうに「ありがとう」と言ってノートを返してくれたのを覚えている。
彼は今どこで何をしているのだろうか。
あの青年も、僕と同じように辛い灰色の毎日を送っていたのだろうか。
不安に襲われ、息苦しくて眠れない夜を幾夜過ごしたのだろうか。
形は違えど、彼も苦しい時期を耐え忍んでいたに違いない。
彼には彼の地獄があり、僕には僕の地獄があったのだ。

僕は浪人の一年間をかけて、行きたかった大学の合格を掴むことはできなかった。
それでも僕は、あの辛かった一年間は無駄ではなかったと、胸を張って言える。
満開の桜の下を教材をパンパンにつめたリュックを背負い予備校に向かって歩いた春も
冷房の効いた校舎から出ると外の熱気にクラクラした夏期講習漬けの夏も
落ち葉の上を歩きながら、なかなか伸びない模試の成績に頭を悩ましていた秋も
この一年間の全てが試される本番を控え、かじかむ手を温めながら机に向かった冬も
全てが美しくも儚く夢散った思い出として、尊い感傷を伴って思い出すことができる。
あの時に感じた「ああ、人生というものは、なかなか思い通りにはいかないものだな」という寂しさと向き合うことはとても辛かった。しかしおかげで、今も辛いときや悲しいとき、そして嬉しいことがあったときに、その気持ちと真正面から向き合うことができる。そして文字に落とし込み、書きつけるとき、あの日々の記憶は僕の筆を助け、ありのままの感情を吐露するのを手助けしてくれる。
人には人の地獄がある。
人それぞれ浪人の辛さ、学んだものは違うだろう。
ある人にとっては厳しかった1年間も、ある人にとっては成長し続けた実りある1年だったかもしれない。
僕にとっての浪人は辛く厳しい長い道のりだったが、あの経験が今の僕の糧になっていることは間違いない。そう胸を張って言うことが、今の僕にはできる。
皆さんの春がより良いものになることを、心から祈っています。
インスタでは爆速で情報発信しているのでぜひフォローよろしくお願いします。
Twitterの方もぜひよろしくお願いします。
<オススメの記事はこちら>
www.nakajima-it.comwww.nakajima-it.com