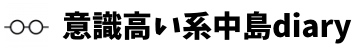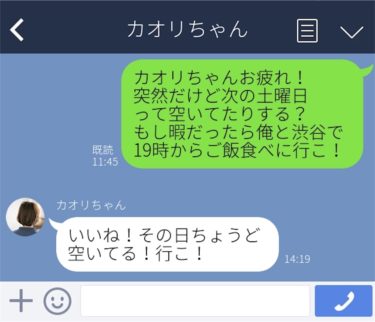朝、目を覚ますとあたりはしんと静まり返っていた。
目覚まし時計に目をやると、まだ6時にもなっていなかった。
いつもの朝、いつもの目覚め。
僕は朝が早い。目覚ましなんてなくとも6時には目が覚める。
今日の朝は昨日までとは打って変わり、肌寒いくらい網戸から流れ込む空気が冷たかった。
薄い毛布が肌とふれあい、かすかな熱をもってはすぐに冷めていく。その心地よい寒暖差を楽しんだ。
しばらくして布団から起き上がった。いつもの日常が始まる。
夏休みだというのにきまりというものは影のようにどこまでも付いてくる。
毎日決まった時間に起き、決まった課題をこなし、決まった時間に寝ることが美徳とされている。その間に個人の自由が差し込む余裕はない。ただ決まりにしたがって生きる。それこそがあるべき姿だと、固められて生きている。
朝一の用を足し、台所に向かう。家族は誰も起きていない。いつもは親、兄弟で騒がしい台所はいつもと違う表情を見せている。
朝日が差し込み蛇口が光を反射している。昨日の洗い残しに溜まった水がその光をまた反射し、天井に不思議な模様が動いている。
冷蔵庫のジーという音がただ無愛想になり続けている。その音も次第に意識の外に追いやられ、あたりは無音になった。
ひとり食パンをトースターで焼き、牛乳をグッと飲み干した。
牛乳なんてちっとも好きじゃない。味はもちろんのこと、その白さが不気味でどうしても好きになれない。ただ牛乳を飲むことは僕らの中での美徳とされている。これを飲めば背が大きくなるらしい。本当かどうか試すこともできないから僕らは毎日牛乳を飲む。飲みたくもないものを毎日飲み顔をしかめる。そんな小さな理不尽が積み重なって毎日ができている。
歯を磨いて外へ出た。さっきまでの肌寒さが徐々に消えつつある。すでに陽は昇り、日差しじりじりと肌を刺す。夏の朝は外より家の方が涼しい。日光が当たらないだけでこれだけ体感温度に差が出るのだから不思議だ。
そんなことを思いながら歩くと間も無く汗が滲んできた。うっすらと額にたまる汗をぬぐいながら歩を進める。
ラジオ体操ほど退屈なものはないんじゃないかと思う。家でもできる体操をしにわざわざ早起きして外に出て、学校の校庭まで出て行かなくてはならない。もちろんクラスのやんちゃな友達や済ました女の子はラジオ体操には来ない。毎日律儀にくるのはおばあちゃんと仲がいいクラスの目立たない友達や優等生しかいない。僕も心の中ではなんで行かなくちゃならないのかと思いながらも、家族に言われるがまま、己の生真面目さに従うがまま律儀に通いつめている。
音楽が流れリズムに合わせて体を動かす。いつもは弟とおばあちゃんと来るのだが、弟は林間学校へ、おばあちゃんは体調が優れず寝込んでいて来ることができない。ただですら恥ずかしさを覚えるラジオ体操だが今日はなおさら恥ずかしかった。
「腕を前から上にあげて 大きく背伸びの運動!」
前ならえより少し上にあげた程度の情けない肘の曲がった腕を見ながら、心底帰りたい気持ちでいっぱいになった。
ただただ同じことの繰り返しで夏はすぎていく。ラジオ体操に行き、宿題を進め、甲子園を見て、お昼を食べ、学校のプールがあれば泳ぎに行き、友達と遊ぶ約束があれば帽子をかぶって外に出た。陽が沈む前には帰りシャワーを浴び、夜ご飯を食べる。
歯を磨いて、アニメを見て、子供でも見られるバラエティを見て親におやすみなさいを告げ、布団で寝る。この平凡なルーティーンを繰り返すことで夏休みはすぎていく。
家に帰ると母親と父親が忙しそうに朝の支度をしていた。テーブルには朝ごはんが準備してある。さっき食べたのは食パン一枚と牛乳。それだけじゃ足りないことをわかってる母親が毎日しっかりした朝ごはんを用意してくれている。
親におはようと挨拶をし卓を囲んだ。テレビから流れるニュースはちっとも面白くない。それを見る親の顔もちっとも面白そうではない。そんなつまらないなら僕に録画したアニメを見させてくれてもいいのにそれは禁じられている。朝にアニメを見るのはよくないのだそうだ。ちっともわからない。むしろ夜にアニメを見てワクワクして眠れないこともあってそっちの方が体に良くなさそうなのに。大人はやっぱりわからない。
どっかの官僚が不正を働いて国会で追及されているニュースを聞き流しながらご飯を食べる。その間にせわしなく母親が朝の掃除を終え、あっという間に着替え、パートに出かけていった。それに続いて父親もスーツに着替え会社に向かう。
リビングに一人になった僕は食器を洗い、テーブルを拭き、おばあちゃんの様子を見にいった。
具合が悪く寝込んではいるものの体調はよくなりつつある。
「やあ弘ちゃん。今日も行ったのかい?」
「行ったよ。起きた時は涼しかったのに始まる頃にはかんかん照りだよ。汗かいちゃった。」
「そうかい。毎日ちゃんと行ってて偉いねえ。」
甲子園を見ながらおばあちゃんが話しかける。夏休みはこうやっておばあちゃんの部屋で甲子園を見るのが定番になっている。
試合が終わるたびに新聞から切り取ったトーナメント表を大切に塗り、どこが優勝するのか楽しみにしている。
この趣味をかれこれ20年以上続けているおばあちゃんだが、肝心のルールは少ししか分からない。フライが上がったらランナーは走っちゃいけないのになんで今、三塁ランナーがホームに走ったのか。バントしてあってファールになったのにどうしてアウトになったのか。おばあちゃんの質問は毎年似たようなものばっかりだ。尋ねられるたびに僕は答える。物心ついたときから変わらない夏の日常。
ちょうど試合が終わり、お昼になった。母が作っておいてくれたお好み焼きをおばあちゃんと二人で食べる。
「宿題は終わったのかい?」
「終わってるよ。夏休みが始まって三日目にはもう全部終わらせたよ。」
「そうかい。弘はかしこいねえ。」
お好み焼きを食べ終え食器を洗い、またおばあちゃんは甲子園を見に部屋に帰っていった。
僕はプールがあるので荷造りをし、再び学校に向かった。
外はうだるように暑い。熱気がまとわりつく。汗はダラダラととめどなく流れ、数メートル先のアスファルトは熱気で歪み、ゆらゆらと揺れている。その揺れる道を一歩一歩進み、ようやく学校へたどり着いた。
夏休みも後半となるとプールにくる同級生はいよいよ少なくなる。家族旅行や帰省などでみんな出かけているのだ。数少ない友達と着替え、プールサイドに並ぶ。陽に焼けた他のクラスの担任の先生がホースで水を撒いていた。おかげで裸足で歩いても暑くない。
先生の指示に従いながら僕らは泳いだ。プールに潜ると水色の底に日光がキラキラとあたりとても綺麗だ。おまけに水の中は音がしない。友達がきゃっきゃと声を上げるなか潜ると、そこには自分だけの世界が広がっている。
息が続く間だけ楽しめる水中の世界。底に引かれた青いラインはどこまでも伸びているかのよう。決して少々濁っているため途中でラインは白いもやの中に消えた。
ふと、様々な色をした小さなきらきらが白い泡を引きながら水中に飛び込んできた。
赤、青、黄、緑。
ゆらゆらと底に向かっていき、下に着く前に拾われるものもあれば忘れられたかのように底に溜まった落ち葉と仲良く沈んでいるものもある。
そのうちの一つを拾い、先生が置いたバケツに向かって投げ込む。ほとんどは的を外れプールサイドに転がり、先生が忙しそうに集めて回る。明らかにわざとあらぬ方向に投げ怒られている生徒もいた。でも先生も生徒も笑顔だ。みんなこのどこまでも自由な夏のひと時を楽しんでいる。
少し高度を落としながらもまだまだ暑いひざしが水面を照らし、無数の光が揺らめいていた。
家に帰り録画してあるアニメを見ているうちに眠くなり、僕はソファで横になった。
水中の運動は疲れる。知らず知らずのうちに全身を動かしていて、落ち着いた途端どっと疲れが押し寄せてくる。
横になるなりまぶたが重くなった。
クーラーが効いた部屋でブランケットに包まれて眠るこのひと時が、たまらなく愛おしい。
ガーというクーラーの音が次第に遠くなり、心地よい昼寝の世界に誘われた。
僕は昼寝で夢を見ることがほとんどない。よほどぐっすりと眠れたのか、いつもふっと目を覚ますと二、三時間経っている。この日も目を覚ますと母がすでに帰宅していた。晩御飯の支度をしている。
「おかえりなさい」
「ただいま」
忙しそうに台所を動き回る母の背中を横になりながら眺め、心の底から安心感を覚えた。
陽は既に傾き始めていた。オレンジの光が窓から差し込みソファに直接降り注ぐ。朝のようなジリジリとさす日差しではなく、クーラーで少し冷えた体を溶きほぐすような優しい日差しだった。
少し体を動かしたくなった僕は軽く散歩をしに外に出た。昼間に比べればだいぶ涼しく、夏の終わりが近いことが感覚でわかる。
遠くで犬の鳴き声が聞こえ、通り過ぎる家々からは晩御飯の匂いがする。
陽は沈みかけあたりが紫色に包まれる。空との色の違いがなくなり、周りと一体化する。もう気にも留めなくなったセミの声が、この瞬間だけやけに耳に響いた。
日没を惜しむかのように鳴くそのけたたましい音が頭の中にこだまする。
子どもながらにもこのような情景には胸がぐっと締め付けられうような切なさを感じる。この気持ちをこの先も忘れずに生きていきたい。日常に潜む心が切なくなる瞬間を5年後、10年後も抱きしめていたいと、強く思った。果たして未来の僕はこの少年時代の心を、将来尚その身に宿しているのだろうかと。
住宅街を抜け公園に着くと、もうみんな帰った後だった。忘れられた水鉄砲が水道の近くに無造作に投げ捨てられている。役目を果たしボロボロになったそいつを拾いあげ、引き金を引いた。
元気なく水がちょろちょろと銃口から流れるだけ。最後の最後まで子どもたちと共に戦ったのだろう。そっとベンチに置き、帰ることにした。すでに陽は沈み、わずかな明かりが西の空にあるだけ。街灯もつき始め、誰もいない拾い公園のグラウンドを照らしている。物寂しいこの景色をなんども振り返りながら、帰路に着いた。
家に着き玄関を開けると、カレーの匂いがした。
「おかえりなさい。今日はカレーだよ。」
家事がひと段落した母の顔が明るい。部屋からおばあちゃんも出てきた。
3人で晩御飯を食べる。父はまだ帰ってこない。あとで一人、ビールでも飲みながら食べるのだろう。
「お母さん、おいしいねえ」
「そうだねえ。お母さんのカレーは最高だねえ。お店も出せるねえ。」
「いっぱい食べてくださいね。」
庭から聞こえてくる虫の声を聴きながら僕らはカレーに夢中になった。もう夜はクーラーが必要なくなっている。秋が近い。
歯を磨いてテレビを見て、早めに眠ることにした。
おばあちゃんと母親におやすみを告げ、部屋に行く。
真っ暗は怖いので、一番小さい明かりをつける。それに今日はいつも一緒に寝ている弟がいない。普段より拾い部屋はなんだか手持ち無沙汰で、空いた空間がもの寂しい。
いつも弟が寝ている方に背を向け、壁のすぐ近くで目をつむった。
もうすぐ夏が終わる。今年の夏も、無事に終わりそうだ。
来年も、またその来年も、何事もなく終わるだろう。
中学へ行っても、高校へ行っても、大学へ行っても、社会人になっても、夏の終わりに感じるもの寂しさは変わらないだろう。
それを表現する言葉は多く知るようになっても、終わりの風景自体は変わらない。
僕自身が成長し、大人になろうとも、必ずそいつはやってくる。
来年も再来年も5年後も10年後も100年後も夏は暑く、熱で景色がゆらめき、汗をかき、そして終わりが近づくにつれ朝の静けさ、夕方の淡い色、夜、窓から聞こえる虫の声が一層感情を揺さぶるに違いない。いや、こればっかりはそうであってほしい。
どんなに時代が変わろうと、心の機微だけは大切にし、それを表現する言葉を探す楽しみだけは失くさずにいたい。
それでも、もし夏が失われてしまうなら、心揺さぶる景色、匂い、温度、そして音が失くなってしまうのならば、僕はまたあの夏へ帰ろう。
幼い頃の思い出はいつでも僕を迎え入れてくれる。
過ぎ去った情景に思い焦がれ、夕焼けに染まる街を見ながら、あの夏の面影を見た気がした。